
感動を生み出す音楽理論の基礎 かえるの合唱は”音楽のすべて”が詰まってる
アナタは音楽が好きですか?
世の中にあるたくさんの『音』。一定の高さ、一定のルールで連続して音が流れると、人はそれを『音楽』と認識します。人は音楽を聴くと笑ったり泣いたり、いろいろな感動を覚えるものですね。
音楽の歴史は数万年も前からあり、人類がはじめて作った楽器は約36000年前の遺跡で発見され、動物の骨に穴を開け笛のような使い方でした。そんな昔から人は音楽に親しみ、音楽を研究し、どうすればより感動的な音楽を作れるか試行錯誤されてきました。アナタが知る音楽は西洋文化から生まれたもので、西洋の楽譜では以下の12音でしか音楽を表現できません。
・ド、ド#
・レ、レ#
・ミ
・ファ
・ソ、ソ#
・ラ、ラ#
・シ、シ#
たった12音だけど、アナタはそんな音楽を聴いて笑ったり、泣いたり、感動したりしてますよね? それはしっかりした音楽理論があって、アナタが聴いてる音楽もその理論に従って作られてるからなんです。
いったいどのような理論なのでしょう?
音が心に与える影響は? 楽譜表記の基本からわかりやすく解説します

ちょっと楽譜をイメージしてみましょう。5本の横線があって、左側にナゾのくるくるりんがあって、そのとなりや左上にヘンな数字が書いてあって、線の中にいくつもオタマジャクシがいて――思い出してきましたか?
「思い出せない!」って方、以下に『かえるの合唱』の楽譜をかんたんに自作してみました。

音楽は『リズム・メロディ・ハーモニー』の3要素で作られています。
・リズム(拍子)
一定の間隔で音が流れる
どんな音楽にも必要な要素
楽譜左部の『音符 = 90』と『4/4』が担当
・メロディ(旋律)
様々な音の高さで音が流れる
音階の上下で曲に変化をもたせる
楽譜左部の『音記号』に加え
5線に描かれる『音符・休符』が担当
・ハーモニー(和音)
同じタイミングで2音以上の音を同時に流す
音楽に広がりや深みを与える
5線に描かれる『音符』を重ねてに表記する
楽譜は『左 → 右』に演奏します。リズムを担当する『音符=90』はそこに書かれた音符を1分間に何回演奏するか? の指標になります(メトロノーム記号)。上記例では4分音符を1分間に90回演奏する、ということになりますね。
5線の下にもうひとつ線を書き、そこに音符をつけると『ド』の音ができますが、これはいちばん左に『ト音記号』があるからです。ト音記号は『下にもう1本線を引いて、そこに描かれた音が“ド“だよ』と指示する記号。これではじめてドレミファソラシドの“位置“が決まったことになります。
楽譜を見てみましょう。さて、ひとつ大きなことに気づきませんか? ――なんと曲のなかでメロディーが、音の高さがどんどん変わっていくじゃありませんか!!
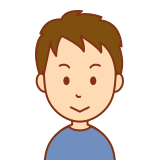
いやいや、そりゃあ音楽なんだから音の高さが変わるなんて”あたりまえ“じゃないか
まあそうですけどちょっと待って下さい。この『音の高さが変わる』ことこそ人に感動を与える重大な要素なのです。音階の変化はそのまま感情の変化に直結します。いったいどういうことでしょうか?
感動を生み出す”音高”の科学
YouTubeチャンネル、Ado:投稿動画より サビの大きな跳躍進行がこころを揺さぶる
音の高さを変化させることで感動が生まれますがただテキトーに演奏しただけで感動できるわけないですよね? ――プロの作曲者はどんなメロディーで聴く人の心を動かすのでしょうか?
一般的に音が上に行く『ド → レ → ミ』などの場合はエネルギーや緊張感が生まれるとされます。気分が高揚したとき低い声になることは少ないですよね? 逆に音が下に行く『ミ → レ → ド』的な場合は落ち着きや弛緩した気持ちが生まれます。
音の高さを変化させない『ド → ド → ド』はそれまでのリズムや音楽の流れを引き継ぐ形となります。
・音の上行
エネルギーや緊張感が生まれる
・音の下行
落ち着きや弛緩が生まれる
・音の保留
それまでの流れを引き継ぐ
音をどのくらいの”大きさ“で変化させていくか? という問題があります。ド → ドのようにある音が同じ高さの音程で進むことを『同音進行』、次の音が2度上下することを『順次進行』、3度数以上離れて上下することを『跳躍進行』と呼びます。
・同時進行
ド→ド→ド など
同じ高さの音程で進行する
ためらい、緊張感などをもたらす
・順次進行
ド→レ→ミ、ミ→レ→ド など
2度以上離れた音程で進行する
穏やかさ、優しさなどをもたらす
・跳躍進行
ド→ミ→ソ、ラ→ファ→レ、ド→ソ など
躍動感や激しさ、強い印象をもたらす
跳躍の”幅“が大きいほど印象も強くなる
作曲者のなかには「曲から作る」という方も多いでしょう。もしかしたらこれらの理論を考えて作曲しているのかもしれませんね。
聴く人にどんな”感動”を与えたいのか?
作曲者は音楽を聴く人に向けて曲を作成します。その曲はエネルギッシュな若者に向けた曲か、失恋のいたみを癒やすための曲か、アニメやゲームなどサブカルチャー層に向けた曲か――曲を聴かせるターゲット層の好みに合わせ曲も変化していきます。
プロの作曲家はこれらの技術をまとめて作曲するのですが、曲は小節と呼ばれる小さなまとまりが集まってできていますね。もういちど上記で紹介した楽譜を見直してみましょう。

かえるの合唱は冒頭2小節でモチーフを作っています。小節は聞いたことがあるでしょう。では『モチーフ』とはなんでしょうか?
曲のイメージを決定づけるモチーフ
YouTubeチャンネル、洗足学園音楽大学/SENZOKU GAKUEN college of Music:投稿動画より
モチーフ(動機)は『曲の代名詞』です。ベートーヴェンの『運命』といえばあのジャジャジャジャーンというメロディーですよね? ――このようにその部分を聴いただけで曲名がわかるような部分をモチーフと呼びます。
かえるの合唱の楽譜を見てみましょう。冒頭から『ド→レ→ミ→ファ』と上行の順次進行で進み、次の小節で『ミ→レ→ド』と続く。なのとなくきれいに着地した印象があるのではないでしょうか? メロディー進行の技法を必要最低限だけ揃えたシンプルな構成です。なにはともあれ、この部分がだれもが「ああ、これはかえるの合唱だ」とイメージするモチーフが完成しました。
もうひとつのモチーフと楽節

かえるの合唱では次の2小節に冒頭のモチーフを発展させたもうひとつのモチーフが描かれています。前半のモチーフを発展させ曲に深みをもたせる機能がありますが、かえるの合唱の場合ちょっと音を上げただけですね。これも音楽の技法を必要最低限だけ使ったシンプルな構成です。
前半と後半のモチーフを合わせた名称を『小楽節』と呼びます。聴き手はここまでを耳にして「なんかのどかで平和な音楽だな」と曲全体のイメージを作っていくのです。
次は『ド→ド→ド→ド』と必要最低限の同時進行。音のひとつひとつがかえるの鳴き声を思わせます。そして最後にもういちどモチーフの流れをもってきて華麗な着地、聴く人に『完結した』印象を与えます。
かえるの合唱は上部と下部ふたつの小楽節で構成されています。ふたつの小楽節を合わせて『大楽節』と呼び、かえるの合唱はこれらすべての要素を必要最低限だけ揃えた音楽理論入門用としても最適な教科書と言えるでしょう。
かえるの合唱が必要最低限もつ要素
・音の上行、下行
・同時進行、順次進行
・モチーフ
・小楽節
・大楽節
子どもたちに『音楽のしくみ』をわかりやすく自然と身につけさせるために必要な要素がぜんぶ揃っていますね。
モチーフが曲の”イメージ”を生む
アナタが『かえるの合唱』を聴いて抱いたイメージはなんでしょう? 歌詞を見なくたって、間違っても都会の真ん中で酒を飲み交わしパーティーを開いてる様子なんてイメージできませんよね? ――かえるが小川のほとりでゲロゲロ鳴いている様子だったり、歌詞を知らなくても音楽を聴いただけで田園連なるのどかな風景や、陽だまりのなかゆったりくつろぐような情景が浮かぶかもしれません。
音楽は『ド・ド#・レ・レ#・ミ・ファ・ファ#・ソ・ソ#・ラ・ラ#・シ』のたった12音で表現する必要があります。限られたリソースで人々に感動を与える作曲家はまさにプロなのですね。
音で人を感動させる技術は、これまでの音楽の歴史から経験的に、また科学的な研究で明らかになたものもあるでしょう。音楽心理学では人のこころと音楽の関係について研究されており、将来的に多くの事実が明らかになっていくでしょう。AIの進化もあるので、もしかしたら『AIが全世界の人々を感動の渦に巻き込む名曲』をクリエイトするかもしれません。そんな未来が訪れるのが楽しみでもありますし、ちょっぴり怖かったりしますね。
アナタはどんな音楽が好きですか?


コメント